
「Home Club」は、お客様により使いやすく便利なサイトを目指し、2022年4月に「MISAWA HOME LOUNGE(ミサワ ホームラウンジ)」と統合し、リニューアルオープンいたしました。「MISAWA HOME LOUNGE」には住まいづくりを楽しく学べるコンテンツや会員特典をたくさんご用意しています。ぜひご活用ください。
> Home Clubアカウントからの100年に1度の大地震がいつ発生してもおかしくないと予想されるうえ、台風やゲリラ豪雨による水害も多発するなど、自然災害のリスクは、かつてないほど増しているといえる。それゆえ、これからの住まいづくりには、防災対策は不可欠だ。平常時、災害発生時、災害後と、トータルで強さを発揮する住まいについて考えてみる。
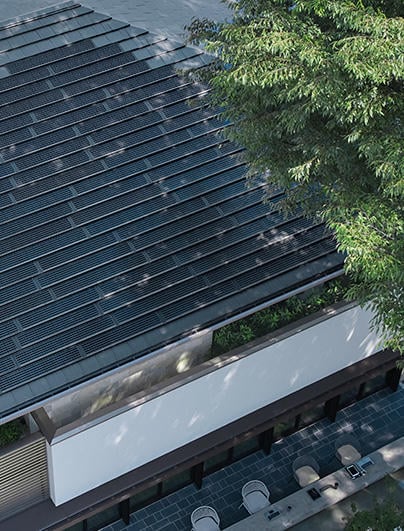

住まい実例やTHINKLIFEコラム、資金計画などの新着記事です。
月刊誌「Home Club」の無料定期購読やデジタルカタログなど、
アカウント登録特典をぜひご利用ください。

皆さまの住まいづくりを応援する月刊誌「Home Club」を6ヶ月無料でお届けいたします。



ミサワホームでは、あなたの住まいづくりをサポートする各種カタログをご用意しています。



住まいづくりやリフォーム、土地活用などのオンラインセミナー・見学会を随時開催しています。お気軽にご参加ください。


200以上の記事の中から、キーワードやタグで記事を検索できます。